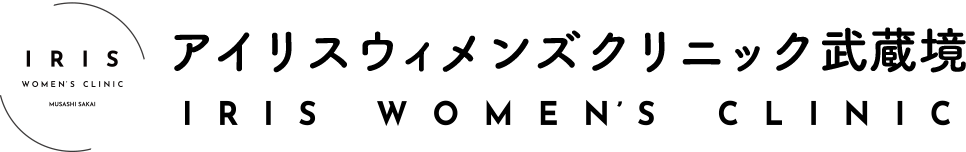排卵誘発とは
排卵誘発とは排卵誘発剤を用いて卵胞(卵子)を発育させ、排卵を促す方法です。通常は排卵障害のある患者様に行いますが、妊娠率を上げるために正常排卵周期を有している患者様にも複数個の卵胞発育を目的として行うことがあります。通常、体外受精に際して、排卵誘発は併用して行われます。
排卵誘発法の種類
排卵誘発法は卵巣刺激の程度に応じて、①低刺激法(mild ovarian stimulation)と②高刺激法(hyper ovarian stimulation)に分けられます。
患者様の状況に応じた排卵誘発法を提案させていただきます。
低刺激法
低刺激法は卵巣への刺激が緩やかなことが特徴です。完全自然周期法よりも採卵できる数は多くなり、妊娠率がわずかに上昇します。 低刺激法は内服薬のみで排卵を誘発することも珍しくありません。状況に応じて注射を併用しますが、その回数はほかの高刺激法より各段に少なく、体や経済的な負担を大幅に軽減することができます。
低刺激法は、1回に採卵できる卵子の数が1~3個で、採卵する卵子の質が高くなるといわれています。そのため比較的高齢でAMHの値が低く、高刺激法で多くの採卵が見込めないと判断された方にも有用とされています。
クロミフェン周期法
クロミフェンには、卵胞の成長にともなって分泌されるエストロゲン(卵胞ホルモン)を隠す作用があります。そのため、実際には卵巣内で卵胞が育っていても、あたかも成長していないかのように脳に錯覚させることで、視床下部からのGnRHの分泌を促進させ、卵巣を刺激します。
レトロゾール周期法
体外受精に使用できるようになった、比較的新しい薬剤です。アロマターゼ阻害剤であるレトロゾール(フェマーラ)を内服します。エストラジオール(E2)が作られるのを抑制し、それにより脳下垂体からの卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されるというメカニズムを利用して、卵巣刺激を行っています。クロミフェンと比較して、子宮内膜の菲薄化や卵巣過剰刺激症候群(OHSS)になりにくいというメリットがあります。
高刺激法
高刺激法は注射の排卵誘発剤を連日使用する方法です。卵巣予備能に応じた卵子数が得られるというメリットがあります。
連日の注射が必要なため、一般的に高価、かつ直接的に卵巣を刺激するため副作用に留意が必要です。
ロング法
ロング法は、排卵周期前の高温期中期から採卵までの毎日、排卵を促すGnRHアゴニスト点鼻薬を、1日3回左右の鼻腔にスプレーします。その後、月経の3日目から排卵誘発剤を6~10日間、毎日注射し、卵胞の状態を見ながら排卵の2日前にhCG注射を投与(排卵のトリガー)します。
ロング法は、卵巣機能に問題がない方、AMH検査でAMH値が高いことがわかった方を中心に、採卵の場合はできるだけ多くの卵子を確実に保存したい方、仕事やプライベートの都合で排卵日を事前に特定し、計画を立てたい方などに行われる方法です。
ロング法は、卵巣を強く刺激して多くの卵子を獲得できる方法ですが、若い女性に多い排卵障害のPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)がある方は、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)のリスクが高いため適用外になります。また、40代前後の高齢にあたる方や、卵巣内に残っている卵子の数が少ない方は、注射の反応が弱くなるため適用外です。
ショート法
ショート法では、月経の初日から採卵前までGnRHアゴニスト点鼻薬を使用し続けてホルモンの分泌を抑え、月経の3日目から排卵誘発剤の注射を7~10日間連続して行い、排卵の2日前にhCG注射を投与(排卵のトリガー)します。
ショート法は、卵巣機能が低下していてAMHの値が低く、ロング法をはじめとしたほかの方法では効果が得られなかった方、発育する卵胞数が少ない方に向いています。成功すれば一度の採卵でたくさんの卵子を獲得することが期待できます。また、投薬期間が短いため、長期的な通院が難しい方に適用することもあります。一方で月経開始から排卵誘発剤の使用による刺激をスタートしていくため、排卵日が読みにくく、計画どおりに採卵したい方には向いていません。
アンタゴニスト法
アンタゴニスト法は月経3日目からFSH/HMG注射などを用いて体内の卵子を育て、ある程度大きくなったらGnRHアンタゴニスト製剤を併用して排卵を抑えます。この流れを、卵胞がしっかり発育して採卵できるまで続けるのが特徴です。
アンタゴニスト法は、あまり質の良くない未熟な卵胞を排卵する体質の人や、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)のリスクがあってほかの卵巣刺激法ができない方、ロング法やショート法で思うような結果が得られなかった方を含め、卵巣機能が極端に低下している方を除くほとんどの方に適用が可能です。一方で、デメリットとしてGnRHアンタゴニスト製剤は、ほかの薬品と比べて値段が高めであり、稀に早期排卵してしまう可能性があるという特徴があります。
PPOS法
PPOS(Progestin-primed Ovarian Stimulation)法は「黄体ホルモン併用卵巣刺激法」という意味の、比較的新しい卵巣刺激法です。その名のとおり、卵巣刺激に黄体ホルモン剤を併用して卵巣を刺激します。月経3日目からrFSH製剤もしくはHMG製剤で卵胞をしっかりと育てながら、デュファストンなどの黄体ホルモン剤を服用し、自然な排卵を誘起します。投薬期間が短いため通院回数が控えられる上、良好な胚に育つことが期待できる方法です。OHSS(卵巣過剰刺激症候群)のリスクも最小限にすることもできます。
一方で、PPOS法は、低温期のあいだに黄体ホルモン剤を経口投与するため、採卵後の子宮は着床に適さない状態になります。そのため、採卵と同じ周期に胚移植を行う「新鮮胚移植」は、原則行うことができません。採卵により得られた良好胚はすべて凍結保存し、次の周期以降に子宮内膜が整った段階で胚移植することになります。
排卵誘発のリスク
世界的にも広く使われており、安全な薬剤の一つですが、以下にあげるいくつかの副作用がございます。
1.多胎率の増加
多胎とは双子、三つ子以上となった妊娠のことです。排卵誘発剤を使うと2つ以上排卵することが多くなるので多胎率は高くなります。自然妊娠でも1%は多胎となりますが、クロミフェンによる多胎率は約4-5%、ゴナドトロピンによる多胎率は約15-20%とされています。多胎の場合、早産などの周産期リスクが高くなります。
2.卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
クロミフェンでは稀ですが、ゴナドトロピンでは起こることがあります。特に体外受精では大量に投与が必要になることがありますので注意が必要です。若年、やせ型、多嚢胞性卵巣症候群などではリスクが高くなります。両側の卵巣が腫れあがり、血管の中の水分が卵巣から浸み出し、腹腔内にたまってしまいます(腹水)。血管内は脱水となり、血栓ができやすくなります。重症化した場合は入院点滴治療が必要となることがあります。