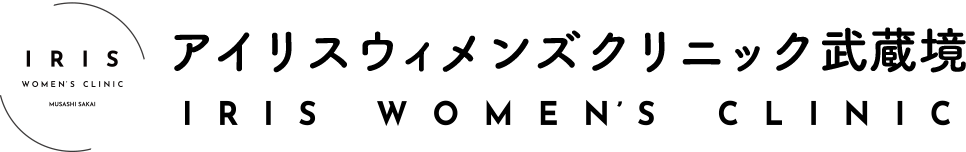当院の体外受精の特徴
当院では出生率追及生殖補助医療(Live_Birth_Rate_Optimized ART)を実践することを診療理念としており、本日現在、以下の6つの柱からなっています。
(今後新たに世界的な高品質エビデンスが出てきた場合、変更する場合がございます。)
- 採卵数maxを目指す
- アンタゴニスト法で誘発
- 採卵9個以下は新鮮胚移植、15個以上は全胚凍結
- 基本胚盤胞移植
- 融解胚移植は自然排卵周期(ホルモン補充療法周期を極力用いない)
- Add-ons(いわゆる”オプション”)は”プラセボ”で利用する
各々その理由を解説いたします。
①採卵数maxを目指す
アメリカ全土の体外受精402,411周期を検討したデーターが2023年のアメリカ生殖医学会誌に掲載されました[1]。
図は横軸が採卵卵子数-縦軸が出生率で、青いグラフが累積出生率、茶色のグラフがその周期初回の胚移植での出生率です。
採卵数が多ければ多いほど、初回胚移植での出生率、累積出生率ともに上昇することが明らかです。
同論文の採卵数-正常受精胚数(2PN)(青)-総胚盤胞数(茶色)のデーターです。
同じく2PN数、総胚盤胞数は一次関数的に増加することが明確です。
次に、2019年に発表された、自然周期と排卵誘発周期での胚盤胞当たりの染色体正常胚盤胞率の報告です[2]。
この報告では
「排卵誘発を行っても、得られた胚盤胞の染色体正常率は低下しない」
ことが示されています。
一昔前に
「低刺激法の方が胚質が良い」
とする考え方があった時期が存在したのは事実ですが、現在ではご覧いただきました通り否定されています。
現代の体外受精の成功は
「染色体正常胚盤胞をいかに得るか?」
にかかっていますから(参照:着床前診断のページ)、採卵数が1個でも多い方が有利といえます。
②アンタゴニスト法で誘発
排卵誘発に関しては、原則ESHRE(欧州生殖医学会)のガイドライン(現行は2019年版[3])に則ります。
ご覧のごとく、全てのシーンでアンタゴニスト法が推奨となっています。
基本的にアンタゴニスト法はオールマイティで、他の方法はアンタゴニスト法に比べ何かしらができなくなる、という足枷が加わります。
例えば
- PPOS法:新鮮周期が利用できない
- ロング法(ショート法):GnRHアナログトリガー(点鼻トリガー)が使えない
等です。
もちろんこれらの方法の長所が確実に有効利用できる場合はこれらの方法を使用しますが(例:PGT-A周期はPPOS法を用いています)、その他は原則すべての状況に対応可能なアンタゴニスト法を用います。
③採卵9個以下は新鮮胚移植、15個以上は全胚凍結
アメリカ全土の胚移植82,935周期を検討したデーターが2018年に報告されています[4]。
横軸が採卵卵子数(1-5個、6-14個、15個以上)-縦軸が出生率で、青いグラフが新鮮周期、赤いグラフが凍結周期の成績です。
ご覧いただけます通り、
採卵数が少ない場合は新鮮移植有利-採卵数が多くなると凍結が有利
となります。
この傾向はその後ランダム化比較試験(2025年)でも確認されました[5]。
本試験は採卵数9個以下の患者さんをランダムに、
「新鮮胚移植を行う群」と「全胚凍結し新鮮移植を行わない群」
に分け、その後の成績を比較したものです。
その結果、新鮮移植あり vs なしで
累積出生率:51.3% vs 44.2%
初回胚移植での出生率:40.1% vs 31.5%
でした。
その結果を受け、JAMA(アメリカ医学会誌)に
「新鮮周期移植は、低成功率が予想される患者さんの体外受精の治療成績をブーストするのかもしれない」
(Fresh Embryos May Boost IVF Outcomes for Women With Low Likelihood of Success)
と題した評論が掲載されました[6]。
過去に
「何でもかんでも全員凍結(全胚凍結)」
というのが流行った時期があったのも確かですが、以上のごとく直近、流れは完全に変わってきております。
以上に則り、
採卵数9個以下は基本新鮮、10-14個で個別判断、15個以上は全胚凍結
を原則方針としています。
④基本胚盤胞移植
初期胚で移植するか?胚盤胞で移植するか?が長らく論争となっています。
そんな中、近年、かなり核心に踏み込んだデーターが公表されてきました[7]。
本試験は、採卵に臨んだ患者さん(採卵2日目に利用可能胚が4個以上)を
「新鮮移植も余剰胚凍結も全て初期胚」vs「新鮮移植も余剰胚凍結も全て胚盤胞」
にランダムに割り振り、その妊娠成績を見てみた、という報告です。
その結果
<累積出生率>
全て初期胚群58.4%(350/599)、全て胚盤胞群58.9%(355/603)で有意差なし
<初回移植のみの出生率>
全て初期胚群29.5%(177/599)、全て胚盤胞群37.0%(223/603)
<総移植回数>
全て初期胚群2.37回、全て胚盤胞群1.99回
であったとのことです。
すなわち、
- 出生率は初期胚でも胚盤胞でも全く同点
- 移植一回当たりの出生率は初期胚不利
- 移植回数も初期胚が多くなる
という結果でした。
以上より、医学的(出生率的)には「どっちでも好きにしていい」となりますが、日本の制度上、体外受精の保険適用回数は胚移植回数でカウントされていくので、患者さんとしては移植回数を減らすことができる「胚盤胞有利」となります。
よって、原則胚盤胞と考えます。
但し、強硬な胚盤胞培養は全滅のリスクを伴いますので、状況説明し、最終判断は患者様判断とします。
⑤融解胚移植は自然排卵周期(ホルモン補充療法周期を極力用いない)
ホルモン補充療法周期は管理が容易なのですが、妊娠成立時の合併症(妊娠高血圧症候群/癒着胎盤など)のリスク上昇が指摘されております。
せっかく不妊治療を行ってまで妊娠成立したにもかかわらず、妊娠中に思わぬ合併症を併発し、万一の不幸な事態となってしまうのは非常に残念なことです。
安全な妊娠→安全な出産→新たなhappyな家庭
こそが不妊治療の最終ゴールであると考えております。
以上よりよほど自己排卵しない/不安定でない限り、排卵周期(自然周期/レトロゾール周期)で融解胚移植を行います。
⑥Add-ons(いわゆる”オプション”)は”プラセボ”で利用する
不妊治療に併用される、いわゆる「オプション」と呼ばれている治療は全て、その効果は証明されていません。
当院では、これらオプション治療の効果は科学的には証明されていない旨を情報提供したうえで、患者様の最終判断に則って使用いたします。
(これらオプション治療を追加することによって、前向きに次回治療に臨まれる方も多くいらっしゃいます)
イギリスには、これらオプション治療のエビデンスをHFEAという国家機関が判定して患者様に情報提供を行っております。
こちらで「赤」で表示されている項目は基本的にはお勧めしておりません。
(着床前診断(PGT-A)は妊娠までの時間短縮の可能性があり、ご提案させていただくことがあります。)
以上のごとく、当院の体外受精は最新の世界的エビデンスに則って、
「出生率をmaxとする」
ことを主眼に治療方針を定めており、本日現在は以上が最良であろうと判断しております。
しかしながら、医学の世界は日進月歩です。
こうしている間にも新たなデーターが出てきて、突然治療方針をガラッと変更させていただく可能性もございます。
常に情報をアップデートし、最新のエビデンスに則った出生率追及型生殖補助医療をご提供することをお約束申し上げます。
[3] ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI. Hum Reprod Open Volume 2020, Issue 2